そもそも学資保険は必要なのか、どれを選んだらよいのか、何から検討したらよいかすらわからないという人もいるのではないでしょうか?
実際に子供が大きくなり、いつも想定外の進路を選ぶ息子たちに想像以上のお金がかかり、私は学資保険があってよかったと実感しました。
そこで、学資保険の必要性や学資保険のおすすめの選び方について解説します。
実際に我が家ではどのように学資保険を決めたのかもご紹介しますので、ぜひ参考にして下さい。
学資保険をおすすめする理由
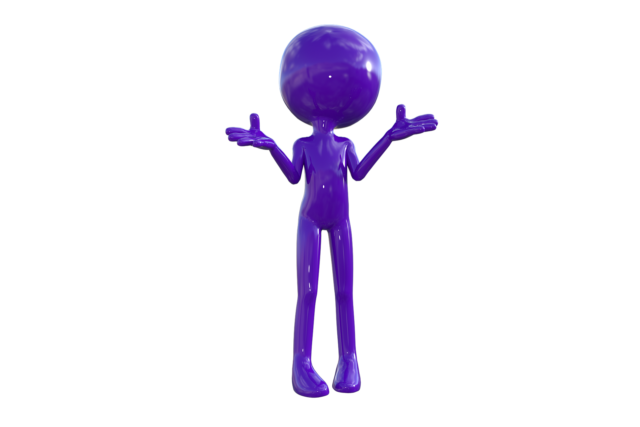
そもそも、どうして学資保険に入るのかというと、将来の子供の教育資金を準備するためです。
学資保険にはメリットも多いので、教育資金として準備をするならおすすめです。
- 払込免除特約が付けられる
- 税金の控除対象になる
まず、払込免除特約を付けられます。
払込免除特約とは、契約者である親にもしものことがあったときに、保険料の払込を免除され、満期金がもらえるという特約です。
親が死亡したり高度障害になってしまったりと、もしものことがあっても子供の教育資金は問題なく準備でき、安心ですね。
また保険ですので、税金の控除対象になるというメリットもあります。
つみたてNISAなど他の方法と組み合わせて準備するのもおすすめです。
学資保険のおすすめの選び方

とはいえ、たくさんある学資保険の商品の中から、いったいどれを選んだらよいのでしょう?
- 貯蓄重視か保障重視かで選ぶ
- 返礼率で選ぶ
- 保険金の受け取り方で選ぶ
貯蓄重視か保障重視かで選ぶ
学資保険の主な目的は教育資金の準備ですので、元本割れしてしまっては困ります。
そのため、保障は重視せずに貯蓄型で返戻率の高い学資保険を選ぶ人が多いのではないでしょうか。
ただ、親が他に生命保険等に加入していないのであれば、同時に保障についても検討するといいですね。
子供の医療保障を付ける医療保険特約もありますが、医療保険特約は付けない人が多いです。
なぜなら子供の医療費には、市区町村による助成制度があるからです。
各市区町村によって助成内容は異なるものの、子供の医療費は無料になる市区町村が多くあります。
返戻率で選ぶ

ところで、返戻率って何かご存知ですか?
返戻率とは、払込保険料の総額に対する、将来受け取れる保険金の割合のことです。
【計算式】返戻率(%)=(お祝い金+満期保険金)÷(払込保険料の総額)×100
この返戻率が高ければ高いほど貯蓄性が上がりますので、学資保険を選ぶ際のひとつの指標となり得ます。
保険金の受け取り方で選ぶ

また、保険金がどのタイミングでいくら受け取れるのかというのが重要になってきます。
一般的には、大学入学時にかかるお金を基準に学資保険で教育資金を準備します。
そのため、18歳になってからではなく、17歳で受け取れるプランがある学資保険を選びたいという人も多いでしょう。
また、在学中の学費を想定して20歳で受け取れるプランや、入学時と在学中とに分けて受け取れるプランを選ぶのもおすすめです。
どのタイミングでいくら受け取りたいのかによって、毎月積み立てる金額も返戻率も変わってきます。
例えば、18歳で200万円を受け取るとしたら、0歳から積み立てたとして月々の支払いは1万円を超える程度です。
200万円じゃ足りないからもっと積み立てたいと思っても、月々の支払額が増えてしまいますので、ここは慎重に検討しましょう。
学資保険は途中で解約すると元本割れしてしまう可能性がありますので、継続することが大切です。
無理のない保険料で継続しましょう。
学資保険で最低限の教育資金を確保し、あとはつみたてNISAなど別の方法との合わせ技で積み立てるのもおすすめです。
学資保険に特化した無料相談サービス
学資保険にも、複数の保険の中から自分に合った保険を選べる無料相談サービスがあります。
一度に複数社の学資保険を比較検討でき、わからないことも相談しながら効率的に選べるのでおすすめです。
なかでも、保険ガーデンプレミア![]() は、学資保険に特化した無料相談サービスサイトです。
は、学資保険に特化した無料相談サービスサイトです。
いつでもどこでも気軽に相談できるので、学資保険選びで迷っている方はぜひ活用してみてください。
【体験談】我が家の学資保険の選び方と利用してみた感想

実は、私が学資保険を検討したのは次男を妊娠中の頃でした。
長男のときは学資保険を検討せず、別の方法で貯めればいいと思っていたのです。
長男と次男は5歳違いますが、その5年の間に、私が教育資金として貯められたお金はごく僅かでした。
これではいけないと思い、次男の産休中に、強制的に積み立てできる学資保険に入ることにしました。
死亡保障や医療保険などは、別途入っていた保険で十分だったので、我が家では貯蓄性重視で学資保険を選んでいます。
フコク生命の「みらいのつばさ」
当時、フコク生命の「みらいのつばさ」だと、医療保険等余計なものを付けなくてもよくて、貯蓄性が高かったので、こちらを選びました。
長男は学資保険に入れるギリギリの年齢で、なんとか入ることはできましたが、遅いスタートとなったため、月々の保険料は次男より2,000円高くなりました。
ちなみに2人とも、入学時にお祝い金を受け取れるプランを選んでいます。
実際これは、長男の中学入学のときなどに想像以上に助かりました。
日本生命の「ニッセイ学資保険」
フコク生命で学資保険を契約してしばらく経った頃に、日本生命からも貯蓄性の高いニッセイ学資保険が登場しました。
もう長男は学資保険に入れる年齢ではなかったので、次男だけニッセイ学資保険にも入ることにしました。
なぜなら、ちょうど学資保険だけでは教育資金としては足りないかもしれないと思っていたところだったからです。
フコク生命でお祝い金を受け取れるので、こちらはお祝い金を受け取らないプランにして、契約者も夫ではなく私にしました。
学資保険を利用してみて
私はどうやら長期にわたる貯蓄は苦手なようなので、保険料として毎月引き落とされる学資保険にしてよかったです。
もちろん他の手段で教育資金を準備できるなら、学資保険でなくとも大丈夫ですが、貯蓄が苦手な人にはぜひ学資保険をおすすめしたいです。
子供が大きくなると、赤ちゃんのときには想定していなかったことも起こります。
「習い事にこんなにお金がかかるとは思わなかった」
「私立の中高一貫校に行かせるつもりなんてなかったのに」
「まさか高校から親元を離れるとは思っていなかった」
などなど、思った以上にお金がかかるのです。
我が家も想定外のことだらけでしたが、学資保険のおかげで無事長男の大学入学費用も支払えましたし、次男の教育資金も準備できつつあります。
学資保険のまとめ
今回は、我が家の体験談もご紹介しつつ、学資保険について紹介しました。
学資保険は、貯蓄性を重視して子供の教育資金を準備するのにおすすめです。
親に万が一のことがあった際に払込免除になるというメリットがあるのも助かります。
赤ちゃんが生まれてからでも遅くありませんが、時間にゆとりのある産休期間中に検討しておくといいですよ。
0歳から加入するほうが毎月の保険料の負担も少なく済みます。
どうやって子供の教育資金を準備するのが良いか、ぜひじっくり検討してみてください。
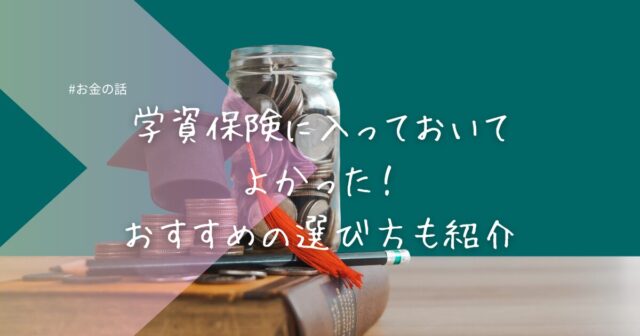



コメント